
ストーリー
モンスター
GB-1ヘプス(CV:関幸司)

早朝のマイスターの実験室で、髪を切る時間も無かったかのような年老いた男が忙しなく動き回っていた。
彼の前では、巨大な2つの車輪が付いた搭乗型兵器が完成しつつあった。
後ろから気配を感じ、年老いた男は振り返りもせずに言った。
"ケケケ…何の用だ?"
"ジゼル…計画は順調ですか?"
誰の耳にも心地の良い美声。ジゼルは何度聞いても慣れないその声に身震いをした。
ジゼルのように分かりやすい狂気ではなく、その内面に宿った…狂気と呼ぶにはあまりにも深く重い影…
ジゼルは無用な雑念を払うために頭を一振りし、エルディールに目を向けて言った。
"…エルディール。歴史を変えるというのはそう簡単じゃないと分かっているだろう?"
"もちろんです。でも、本当に変える必要があるのか…それは再考すべきもんだいですが。"
"ケケケ…またその話か?すべてを証明したのに、まだ私を信じられないんだな。"
エルディールは気分を害したのか、目をヘビのように細めたジゼルを見下ろした。
未来から来た男。
時間を超えるのは誰にでもできることではない。
目の前にいる年老いた男は確かにすべてを証明してみせたが、最も本質的な命題を証明できていなかった。
『この男の話を信じて過去を変えることが、本当に創新世紀の予言のためになるのか?』
もちろん、ジゼルが言っていた情報は自分の正体を知っているという事実だけでも証明されたようなものだった。
エルディールの正体を知る者は天界にもわずかしかいないから。
それでも彼を完全に信じられない理由もやはり一つだった。
"あなたが言っていたその者は…本当にここへ来るのですか?"
"その者?ああ、冒険者のことか。"
ジゼルは不機嫌そうに顔を背けた。
常に狂気を感じさせるものの冷静で計画的なジゼルは、唯一「冒険者」のこととなると動揺を隠せなくなる。
それが気がかりだった。エルディールがやろうとしていることは、絶対過剰的になってはいけないことだからだ。
ジゼルは黙って作業を再開し、エルディールは彼が作っている「未来を変えるための」兵器を見つめた。
彼女はふと、まだ解決していない命題を思い浮かべる。
彼の話を信じてこれから起こる過去を変えることも、予言の過程に含まれているのだろうか?
もちろん、それはジゼルにもエルディールにも証明できない。すべては起きてみないと分からないのだ。
あらゆる存在は最後の息を吸い込むその瞬間のたびに初めての経験をしているのだから。
変えようとする者たちも…それを阻止しようとする者たちも…
今、この一連の事件がどのような変化を呼ぶのか、今はまだ誰にも分からないのだ。
GB-2イデンティテイト(CV:前田雄)

"ボクが作った自律システムの設計図を一度見てもらえませんか?"
オードリューズが袋から取り出したピーナッツを口に突っ込みながら言った。
恐らく、会議に来る前にエターナルフレイムの誰かからもらったのだろう。
"オードリューズ、ゲイボルグに自律性は入れないことにしたはずだけど?"
クリオは言葉とは裏腹にオードリューズに渡された設計図をじっと眺めながら答える。
オードリューズはクリオの言葉に唇を尖らせてもう一度言った。
"どう考えても、歩行制御から迎撃防御システム、それから今回クリオが追加する予定の次元移動装置まで全部を一人でコントロールするのは効率が悪すぎるんですよ。"
その瞬間、刺激的な匂いが鼻をついた。
ツンとする火薬の匂い、そして竜族の血の匂い。
ボルガンだった。
"ハハハ!どうしてそう思うんだ?俺もスタークもそれくらいは十分できるぞ。俺は今からゲイボルグに乗ってバカルの顔をぐちゃぐちゃにしてやることを想像してワクワクしてるんだ!"
遅れて入ってきた彼は、力強く笑いながらオードリューズの背中をバンバンと音がするほどに強く叩いた。
だが、その坑道とは裏腹に、顔には疲れが色濃く表れていた。
"それはお二人だからできることでしょう…?それに、操縦が完璧にできても、操縦者の安全まで考えたら自律システムに全権を預けた方が良いと思うんですよね。"
"心配無用!操縦室はゲイボルグが作動している限り、この世で一番安全な場所になるようにできてるからな。"
"あの人がどうしても自分で作るんだって言い張るから…"
ラティは力なく鼻を鳴らしてタバコに火を点けた。
ゲホゲホッ!
モクモクと湧き上がる白い煙の間に、か細い咳が響いた。
"ああ、ごめん。つい、癖で火を…!"
"私は大丈夫です…!"
ジェンヌの気まずそうな声。
ラティがジェンヌを見つめながら慌ててタバコの火をもみ消す。その一瞬、私とジェンヌと視線が交錯した。
お互いだけが分かるほど小さな笑いを交わした後、改めてオードリューズに目を向ける。
"じゃあ、ゲイボルグが破壊されたら?"
"無敵のゲイボルグが破壊されるなんて、ありえないだろう?ハハハ!"
"もしくは…システムに自律性を入れるのではなく、単純に自動補助の手段として活用するのはどうです?"
"ジェンヌ、良い意見だね。エルディール、どう思う?"
状況を見守っていたクリオは静かにエルディールに質問を投げた。
"私は…。"
エルディールは話し出した途端、ざわついていた周囲の音が突然止んだ。
重い沈黙。
どんな案件であっても、会議はこうして進められた。
各自の意見を述べた後、エルディールが話し出すと全員が息を殺したように彼女の口元に集中する。
そして彼女はその沈黙に応えるかのゆうに、どんな問題にも常に完璧な解決策を提示してきた。
"ゲイボルグは自律システムが制御すべきだと思います。まだ決まってもいない搭乗者の判断に天界の運命を任せるよりも、私たちの力で作ったシステムの方がリスクが少ないはずですから。それに、私たちはこれまで多くの全自動メカニックを作って来ましたし、実際の戦闘でも立派な成果を上げているでしょう?"
エルディールの発言に全員が頷いた。
しかし…
"テネブ。あなたはどう思いますか?"
それでも、常に彼女は私に決定権を握らせてくれた。
いや、いつも皆が私の決定を待っていた。
全マイスターの視線がエルディールから私に移される。
もう一度、でもさっきとは違う静寂がその場を満たす。
"テネブ。"
ジェンヌの柔らかい声に、私はマイスター一人一人を見渡した。
そして、ゆっくりとペンを取り、設計図の修正を始める。
"…補助装置として作った方が良さそうだな。"
言い終えると、マイスターたちは待っていたかのように、すぐにその装置について論じ始めた。
"ハハハ!じゃあ、こいつの名前は何にしようか?"
"私が仮で付けた名前はゲイボルグの自我という意味なんです!もう自律システムではありませんが…それでも良い名前だと思いませんか?"
ただ一人、エルディールを除いて。
GB-3エネギー(CV:高柳知葉)
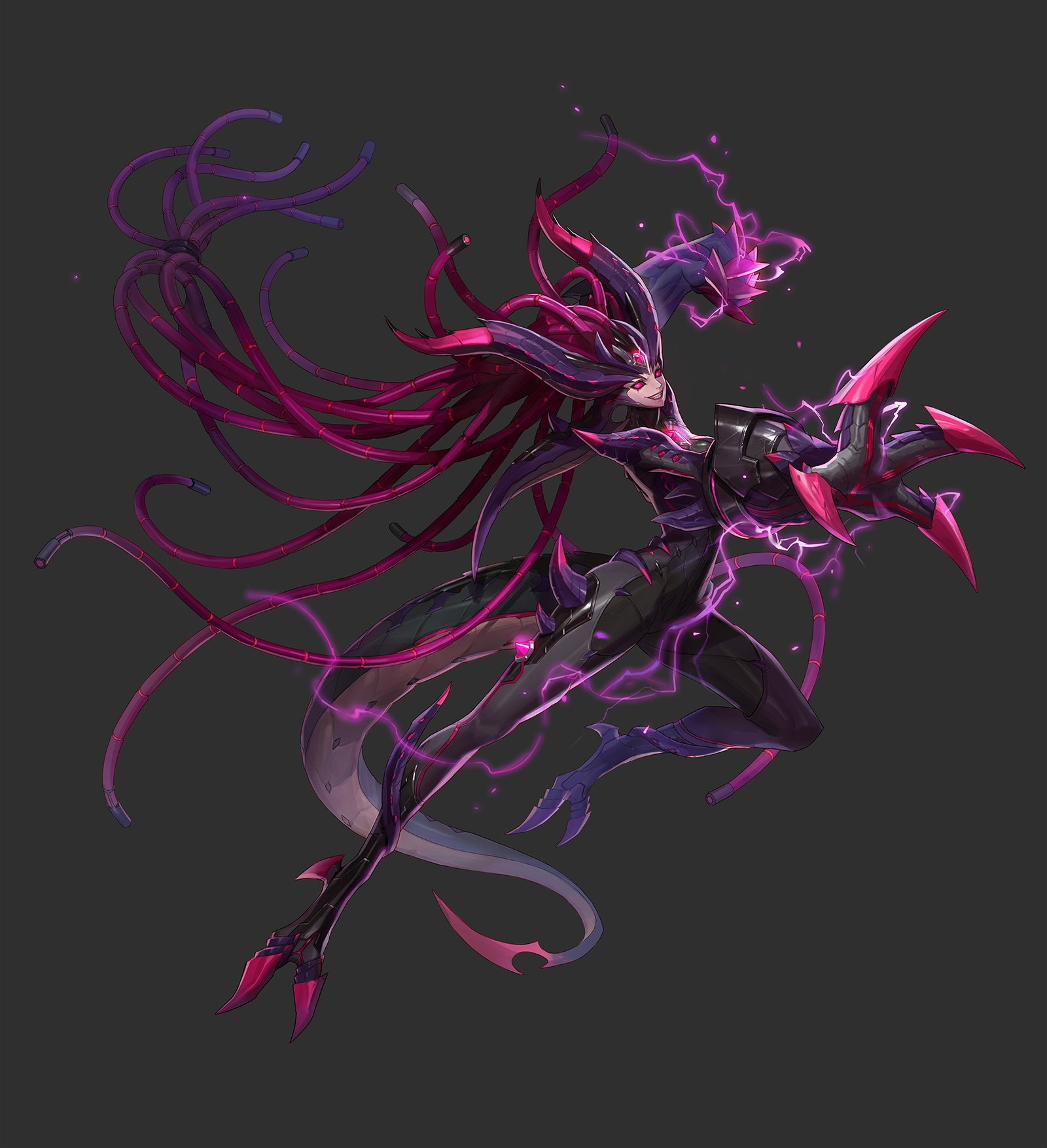
///---------[ 軍事 ]---------///
///-[1級秘密]---[CONFIDENTIAL]-///
警告
*許可を得た者以外の取り扱いを禁ず
///---------[ スペック ]---------///
兵器名 : 「GB-3エネギー」
種類 : 汎用竜人型生体戦闘兵器
全長 : 302 cm
重量 : 1207 kg
握力 : 10.5t
主武装 : 竜人生体、胸部エネルギーコア
本武装 : 各関節地点のエネルギーコア14個、前頭葉内の制御用小型電流器
///---------[ 報告 ]---------///
----/-- : 実験室6区域内部、ドラカ・アンスト4機、カルテ・ルフト7機により捕獲。出動装備全損。作戦担当隊長スターク
----/-- : 正存確認、冬眠システム進行
----/-- : 冬眠システム中に研究を進行
……
----/-- : 冬眠システム中の研究を中断/マイスター級会議、研究進行否決。無期限冬眠。
……
----/-- : ジゼル・ローガンに権限移管
----/-- : ジゼル・ローガン主管。実験進行、1次エネルギーコアの安着実験
----/-- : ジゼル・ローガン主管。過負荷により発作発症
----/-- : ジゼル・ローガン主管。鱗が落ちる症状
……
----/-- : ジゼル・ローガン主管。実験進行、23次エネルギーコアの安着実験
----/-- : ジゼル・ローガン主管。鱗の自然復旧確認
----/-- : ジゼル・ローガン主管。エネルギーコアの安定化確認
……
----/-- : ナサウ森林7番区域付近で作戦中に騒ぎ
----/-- : 24次実験、制御再安定を確認。異常なし。
----/-- : エネルギー生産室へ移動。
----/-- : エネルギー生産室警
"…警戒、異常…なし…現在の時刻…"
"中佐…"
"もういい!何時かと聞いている。"
二人の隊員が、巨大な竜人の入ったインキュベーターの前に立っていた。
パネルを操作している、中佐と呼ばれた隊員の手は明らかに焦っていた。
"ちゅ…中佐…。いくら何でも危険すぎやしませんか?少し前にも洗脳が解けて騒ぎになったそうですし…。"
"..."
"我々にどうにかできる問題なのか…"
"じゃあ、お前が止めるか?"
"ですが…"
"スターク隊長ですら難しいかもしれないとおっしゃったんだ。俺は何度もあの方と一緒に戦場へ出たが、そんなことをおっしゃったのは最初で最後だった。"
"中佐…"
"どのみち、ゲイボルグさえ守ればいいんだ。"
中佐がパネルから手を離すと、煙が漏れるような音と共に巨大な竜人の身体が姿を現した。
人間を見下ろす瞳には、異種生物に向けた明らかな敵意が宿っていた。
"おい、洗脳装置は…まともに働いてるんだろうな?"
"そのはずですが…"
"そのはずなのに…あんな動きをするのか…?"
"え…?"
竜人の影が二人を覆っていた。
"まずいッ…"
バキッ!
"ひ…非常事態…!ひ…"
バキッ!バキッ!
竜人が手に付いた血と破片を払いながら歩き始める。
紫色の鱗が、赤い血液で濡れてぬらりと光った。
やっと静かになったか。
虫けらどもめが…。
人間二人を殺したにもかかわらず、頭の中の雑音は消える気配もない。
叱られないためには…挽回しなければ。
あの方が喜ばれるような方法で。
巨大な力が、風のように吹き込んでくる。
すべての竜の父が起こすその風のおかげで、一瞬雑音が消えた。
エネギーは爽快さを感じながら、ゆっくりと体をほぐしはじめた。
GB-4ディリゲント(CV:高田紗希衣)

ジゼル様の命令に従って行動。
ゲイボルグのメイン動力源を守り維持。
妨害する侵入者は全員抹殺。
…最優先命令、天界を守ること。
目を覚ました瞬間に浮かんだのは、この4つの原則だった。
その後追加された様々な知識を受け入れながら、天界とエターナルフレイムの現状、そして自分が作られた理由を知った。
現在、エターナルフレイムの状況はよろしくない。
"現在の補給状態"
不足
"生産された量産型武器の数量"
不足
"…現在実験室内で戦闘可能な生体反応確認"
不足
竜族はどんどん包囲網を狭めているにもかかわらず、何もかもが足りなかった。
天界の最後の希望であるゲイボルグも未完成の状態だ。
マイスターの支柱だったテネブまで何らかの理由でプロジェクトから抜けてしまった。
"…絶望的な状況。"
だから、他のマイスターたちはこの状況をするためにジゼル様を利用して私を作り出した。
天界のために命をかけて戦っている者たちの犠牲を減らし、ゲイボルグが完成するまでここを守るために。
それだけが、彼等にとって最後の希望だから。
考えをまとめた後、すぐにプログラムを実行した。
私の存在が消えても、その思いを実らせるために。
"…保護プロトコル設定。"
すべては天界と…
"侵入者殲滅モード実行。"
ジゼル様のために。
GB-5ペルハンスターク(CV:財満健太)

エターナルフレイムの隊長、スタークは何でもよく憶えている方だった。
彼は初めての分隊員たちのことも記憶している。
服の修繕が得意だったルテリン一等兵はナサウの山が好きだった。彼はそこで竜族の爪で腹部を引き裂かれた状態で発見された。
カリヤ上等兵は虫が嫌いで、四歳年下の妹がいた。竜の吹く炎で肺を焼かれて戦死した。
トリステン兵長は疲れたというのが口癖で、スタークとはよく揉めもしたが一番親しくもあった。竜族に掴み上げられた後、地面に投げ落とされて戦死した。
新兵だったデボンはスタークを慕っていた。警戒中に竜族の魔法でねじり曲げられ、戦死した。
スタークは彼らの死に方も、最期の吐息も、簡素な隊員たちの葬儀の匂いまですべて記憶していた。
彼はさらに過去のことも忘れていなかった。
初めてエターナルフレイムで訓練を受けた時、銀髪の優男が自分のとなりにいたことも憶えている。
自分が彼を見て早々に訓練から脱落するだろうと思ったことも、彼が訓練を見事終えて驚いたことも憶えていた。
その後、訓練兵たちの飲み会で、その優男が魂を売り飛ばしてでも天界を守り抜くと静かに語った時の、あの熱いまなざしも鮮明に記憶していた。
そしてマイスターの長となった彼の隣で、隊長としてエターナルフレイムの誓いを叫んだ瞬間、
"エターナルフレイムは最後の瞬間まで竜に向けて引き金を引き…"
その瞬間、頭の中に浮かんだ、消えることのない記憶。
"息絶えるその瞬間にも消えない炎で竜を殺し、"
隠れろという父の言葉にベッドの下で必至に咳を我慢したこと。ギラギラと光る竜族の眼。
"結局竜によってその命落とす時…初めて我らの使命を全うするであろう。"
もう誰にも自分のような悲しみを経験させてはならないという固い誓い。 そのすべてを、スタークは忘れていなかった。
そして今、彼は培養液の中で、自分の脊椎の中を冷たい液体が満たしていくのを感じていた。
自我、理性、自分、記憶、すべて忘れるだろう。
ゲイボルグと天界を守る一つの兵器として生まれ変わるのだ。
ガサガサと割れるような声が彼の耳元で囁いていた。
…今、私は何をしているんだ?
確かにテネブが裏切りを…
テ…ネブが…裏…切り…?
ネブ…ゲイボ…
ゴホッ。
最後の泡と共に意識が失われた。
スタークの手、今や手とは呼べないものになり果てたそれに、古くて焦げたドッグタグがいくつか握られていた。
まるで、銀色の萎れた花束のように⋯。
エターナルフレイムの隊長、スタークは何でもよく憶えている方だった。
彼は自分を失った今も、何も忘れていなかった。